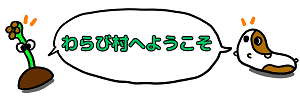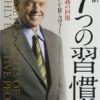【本訳とは】
読書をすることによってもたらされる恩恵は素晴らしいもの。こんなに素晴らしい恩恵を享受できるのが読書好きに限られるなんて、読書好きの私にとっても悲しいことです。外国語の知識がなくても、翻訳されていればその内容を理解できる。そんな翻訳のように、読書が苦手な人や本を読む時間がなかなか取れない人のために、名著といわれる本の内容を出来るだけ分かりやすく伝える活動を”本を訳する(=分かりやすく解説する)”という言葉から”本訳(ほんやく)”と名付けることにしました。
前回までの内容
1冊目 本訳『7つの習慣』第二回:相互依存とP/PCバランス
1冊目 本訳『7つの習慣』第三回:第一の習慣 自分に責任を持つ
1冊目 本訳『7つの習慣』第四回:第二の習慣 目的地をはっきりさせる
1冊目 本訳『7つの習慣』第五回:第三の習慣 重要なことに集中する
1冊目 本訳『7つの習慣』第七回:第四の習慣 お互いの利益を考える
1冊目 本訳『7つの習慣』第八回:第五の習慣 相手のことを本当に理解する
1冊目 本訳『7つの習慣』第九回:第六の習慣 相乗効果を得る
本訳『7つの習慣』第十回では、第七の習慣についてまとめます。
第七の習慣は自分をメンテナンスする習慣
最後である第七の習慣とは、自分をメンテナンスし、効率性のアップを図る習慣です。
この習慣は刃を研ぐ習慣と例えることもできます。
第一の習慣で、自分は野菜を自由に切ることができると気づき、第二の習慣で、どの野菜をどの刃で切るのかを選択し、第三の習慣で実際に切り始め、第四、第五、第六の習慣で誰かと協力して切る・・・
これだけでも充分良さそうなのですが、もしこの刃の切れ味が悪かったらどうでしょうか?
せっかく頑張っているのに、切りにくくなんだか勿体ないですよね。
刃を研ぐと効率も上がります。
このように第七の習慣とは、習慣に磨きをかけ向上させる習慣といえます。
肉体的、精神的、知的、社会・情緒的側面のそれぞれを磨き向上させるのです。
これは自分自身に投資をすることと同じ。
しかも投資した分、いやそれ以上の利益を期待することができます。
けれども、これは”緊急ではないが、重要である”②の領域のため、主体性を発揮しなければなりません。

では具体的にそれぞれの側面について、どのように行動することが、磨き向上させることになるのか紹介していきます。
肉体
肉体を磨き向上させるとは、自分の身体を大切にすることです。
バランスのとれた栄養のある食事、十分な休養、定期的な運動を心がけることです。
運動することの最大のメリットは、第一の習慣である主体性という精神的な筋肉を鍛えることにあります。
精神
精神を磨き向上させるとは、自己リーダーシップを発揮することであり、これは第二の習慣に深く関わっています。
この方法は人によって様々ですが、『7つの習慣』の著者であるスティーブン・コヴィーの場合は、毎日聖書を読むこと、祈りと瞑想をすることを行っています。
他にも、名作といわれる古典文学や素晴らしい音楽を聴くこと、自然の中を歩くなども精神を磨く方法として効果的なので、自分に合った方法を選ぶと良いでしょう。
知性
知性を磨き向上することは、正式な教育によって行われます。
そのため学校を卒業すると、多くの人の知力は弱体化すると言われています。
定期的に優れた本を読むこと、幅広い読書をすることで、知性を磨くことができ、磨かれた知性は第三の習慣である自己マネジメントの習慣の支えになってくれます。
社会・情緒
これは第四、第五、第六の習慣に深く関わっています。
これを磨くには、ほかの人と接する活動を通して行うしかありません。
自分の安定性を発揮して、相手を理解することを意識しましょう。
肉体、精神、知性、社会・情緒という四つの刃をバランスよく研ぐことで、7つの習慣を実行する能力が高まります。
そういう意味で、第七の習慣は、自分をメンテナンスして、良い状態に保ち、効率性を上げる習慣なのです。
まとめ
・第七の習慣とは、自分をメンテナンスし、効率性のアップを図る習慣
・肉体、精神、知性、社会・情緒という四つの刃をバランスよく研ぐこと
これで七つの習慣全てを学びました。
次回の最終回では今までの内容をさらに簡単に振り返りまとめます。
それでは~。