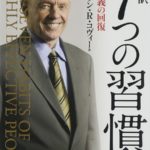
1冊目 本訳『7つの習慣』第三回:第一の習慣 自分に責任を持つ
スティーブン・コヴィーの世界的名著『7つの習慣』を出来るだけ簡単に分かりやすく本訳していきます。第三回は一つ目の習慣である第一の習慣についてです。
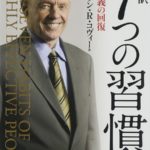
スティーブン・コヴィーの世界的名著『7つの習慣』を出来るだけ簡単に分かりやすく本訳していきます。第三回は一つ目の習慣である第一の習慣についてです。
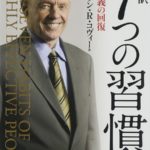
スティーブン・コヴィーの世界的名著『7つの習慣』を出来るだけ簡単に分かりやすく本訳していきます。第二回は、相互依存そしてP/PCバランスについてです。
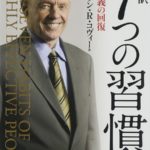
スティーブン・コヴィーの世界的名著『7つの習慣』を出来るだけ簡単に分かりやすく本訳していきます。第一回では、そもそも7つの習慣とは何なのか、何故7つの習慣を身につけるべきなのかについてまとめます。

今回は、TEDのジャドソン・ブルワー氏による「悪い習慣を断ち切るシンプルな方法」という講演が面白かったのでその内容を紹介します。

今回は映画『アイ・アム・サム』を振り返り、日常にも活かしたい心構えを考えていきます。

今回は、映画『アバウト・タイム~愛おしい時間について~』の印象に残った名言・名場面を振り返り、日常にも活かしたい心構えを考えていきます。

「The Man」はテイラースウィフトが日々感じている男性優位社会に対する疑問や皮肉が込められている曲です。今回はこの曲について私が思うことを紹介します。

報酬を与えることで、相手のモチベーションを低下させてしまう「アンダーマイニング効果」について、わらび君ともるもる君の会話から紹介します。

「世界をよりよい場所に変えたいなら、まずは鏡の中の自分を変えよう」と『Man In The Mirror』の曲の中でマイケルジャクソンは私たちに訴えます。今回はこの『Man In The Mirror』の歌詞の内容を紹介します。

私たちが感じる、体や精神的な疲労感・・・それは実際に体力や精神が限界にきているわけではなく、脳が疲労感を作り出しているのです。今回はこの”脳が作り出す疲労感”について紹介します。

モデルのキャメロン・ラッセルは言います。「イメージの持つ力は強烈です。しかし、それと同時にイメージは表面的なのです。」と。彼女の言う通り、イメージは文字通りイメージでしかなく、そのものの本質を表しているわけではないのです。

「自由であればあるほど良い」という認識が広まっている現代社会ですが、本当にそうなのでしょうか?実は「自由」であることが私たちを不幸にしているとしたら?今回はこのことについてバリー・シュワルツ氏のTEDの講演から考えていきます。
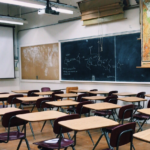
学校は私たちに学びの場を提供してくれる場所。でもその学校が私たちの創造性や可能性を潰してしまっているとしたら・・・。今回は学校教育の問題点についてケン・ロビンソン氏の「学校教育は創造性を殺してしまっている」というTEDの講演から考えていきます。

最近流行っているStudy with me(一緒に勉強しよう)動画。「この動画を流しながら勉強するといつもより勉強が捗る!」など視聴者の側からは嬉しい声があがっていますが、ふとある疑問が湧いてきました。それは動画投稿者に対する懸念です。

テレビを見ることは害でしかありません。テレビを見続けると、考える力が衰え馬鹿になります。馬鹿になりたくないなら、とっとと見るのをやめるべきです。今回はテレビを見るのをやめるべき3つの理由を紹介します。

コロナに疲れている人たちへ、テレビを見ることを止めることです。テレビの報道は私たちの恐怖心を煽る内容のものばかり。こんな内容を毎日見ていたら、疲れてしまうのも当然です。だからまず、テレビを見るのをやめましょう。

一度観たら忘れられないミュージックビデオ「I Could Be The One」。このミュージックビデオにはどんな意味が込められているのか、考えたことをまとめます。

誰かを褒めることは良いことと思いがちですが、もしかするとその褒め言葉が相手にプレッシャーを与え、苦しめているかもしれません。どんな褒め言葉が相手を追い詰めてしまうことがあるのか考えてみましょう。

「他人から認められたい」「褒められたい」と思う欲求、つまり承認欲求は人間なら誰しも抱くものです。しかし、「褒められたい」と願うことには、ある種の危険も潜んでいるのです。

不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句これらを五戒と言ったり、地獄言葉と言ったりします。五戒を一言発してしまうと良くないことが自分に降りかかるといわれています。「言いたくないのについ言ってしまう!」でも大丈夫。一番大事なのは「気づく」ことなんです。