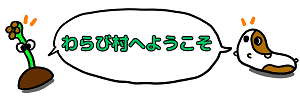ケン・ロビンソン氏の「学校教育は創造性を殺してしまっている」というTEDの講演を視聴しました。
「Do schools kill creativity? :学校教育は創造性を殺してしまっている―ケン・ロビンソン」クリックするとYouTubeで視聴できます
現代の学校教育は数学と語学に重きを置いており、芸術は軽視してしまっている。その結果、子供たちが本来持っている創造性を殺してしまっている、という内容です。
この講演を聴いて、確かに学校教育は芸術を軽視していると共感しましたが、私はそもそも学校の芸術の授業のありかたにも問題があると思っています。
今回は、このことについて語ります。
芸術における成績ってなに?
私が学生だった頃、成績表を受け取る度に思っていたことなのですが、美術のAや5っていったいどういう意味なのでしょう。
逆に美術の成績が1って、どういう絵を描いたらそう評価されるのでしょうか。
私が思うに、美術にそもそも成績という概念があるのがおかしいのではないかと思うのです。
私は絵に上手、下手はないと思っています。
全て味なんです。
それなのに授業では「こうしなさい」「ああしなさい」「それはおかしい」「間違った描き方だ」と教えられます。
そして出来上がるのはみんな似たような絵。
教科書に載っているコピーのような絵が大量に出来上がるんです。
それで一番高く評価されるのは、一番教科書のお手本に近い作品。
私はこの光景を見る度に、「なにかおかしいのでは?」と思っていました。
間違った?描き方をすると注意されるので、美術の授業が嫌いな人もたくさんいました。
でもその人の自由帳とかを見せてもらうと、けっこう面白い絵描いているんです。でも何故か美術の授業では評価されない。
美術の授業で評価されるのは、美術の先生の好きな描き方をできるだけ忠実に真似ようとした人だけなんです。
美術の先生が気にくわなかったり、理解できない絵を描いても1しかもらえません。
1の評価をもらっても、それは美術の先生には理解できない絵を描いたということだけだから、気にしなくていいのに、多くの人が大人になるまでに、このことが理由で絵を描くことが嫌いになっていきます。
その中には、ケン・ロビンソン氏が講演の中でも言っていますが、天才的な才能を持っていた人も含まれているはずです。
なんのための成績なんでしょう。
私は美術に成績評価は不要だし、そもそも評価するのは不可能だと思っています。
不得意な人には苦痛でしかない音楽の授業
学校の音楽の授業もなかなか不思議です。
楽器を弾くのが得意な人、歌を歌うのが得意な人、踊るのが得意な人、そうじゃない人。
いろんなタイプの人たちがいるのに、学校の音楽の授業は、全ての人に全てのことをやらせようとしています。
上手に歌えないと、上手にリコーダーが吹けないと、上手に踊れないと、音楽でいい成績はもらえません。
こんなにオールマイティーな人ってプロでも少ないと思うのですが、学校はいったいどんな人物に育てようとしているのでしょうか。
私は、実技的なことは専門教室に任せて、学校の音楽の授業ではもっといろいろな国や民族、ジャンル、時代の音楽に触れた方が良いと思います。
体育の授業が走ることを嫌いにさせる
私は今、ジョギングを趣味の一つとして行っていますが、学生時代は走ることがとても嫌いでした。
「今は走ることが好きなのに、どうして学生の頃は嫌いだったんだろう」と考えてみたら、理由は簡単に見つかりました。
それは、体育の授業では、自分のペースで走らせてくれないからです。
走るペースは人それぞれです。
時速12キロで走るのが気持ちい人もいれば、時速5キロがちょうどいい人もいます。
この自分にあったペースを間違えると、走ることがとても苦痛になります。
つまり、楽しく走るためには自分のペースを見つけ、そのペースで走ることが大事なんです。
けれど体育の授業は、このことを教えてくれませんでした。
のろのろ走っていると(本人は限界まで走っている)、「もっとペースをあげろ!」と怒鳴られたりします。
これじゃあ走ることが好きになれるはずがありません。
私は最初、歩くくらいのペースから始めました。
そして少しづつ速く走れるようになっていきました。
本来はこんな風に本人のレベルに合わせて、走るべきなんです。
だから遅すぎるペースなんていうのも存在しません。
全体と比べて指導するのではなく、もっと個人の成長に焦点を合わせた体育の授業だったら、走ることが嫌いになる人もだいぶ減ると思います。
学校がすべて正しいとは思わないこと
学校って教育を受ける場なので、学校は正しい存在だと思いがちです。
けれどケン・ロビンソン氏も言っているように、学校があらゆる創造性を殺してしまっていることがたくさんあるんです。
絵を描くことが嫌いになったり、音楽離れしたり、走ることが嫌いになったりするのもこの理由からです。
美術の成績が1だとしても「私には絵の才能は皆無なんだ」と思わないでください。
学校では評価されなくても、世の中からは評価される可能性が多いにあります。
音楽の成績が1でも、音楽そのものを嫌いになる必要はありません。
好きなジャンルの音楽、楽器を見つけてみましょう。
体育の授業で走ることが嫌いになっていても、遊びで一度走ってみてください。
走ることは苦行ではありません。本当は気持ちよく、楽しいことです。
苦痛に感じるのは体育の授業の仕方に問題があるからです。
私が伝えたいことは、「学校のいうことが全て正しいとは思わないで欲しい」ということです。
勿論、学校はいろいろな知識を教えてくれる有難い場でもありますが、だからといって100%鵜呑みにしないで欲しいのです。
先生が「それは間違っている」といっても本当に間違っているのかは分かりません。
なにか「ん?」と引っかかったなら、その感覚を大事にしてください。
「学校でこれはおかしいと言われたから、多分おかしいんだろうな」といって自分の中にある創造性の芽を摘んで欲しくないのです。
偉大な発明家や画家などの偉人には、独学で学んだという人が本当に多くいます。
こういった偉人たちは、独学だったからこそ、創造性や可能性の芽を摘まれなかったおかげで成功を収めることが出来たのだと思います。
だから自分の持つ感性やアイデアを大事にしてください。
最後にマリリン・モンローの名言を紹介して終わります。
たとえ100人の専門家が「あなたには才能がない」と言ったとしても、その人たち全員が間違っているかもしれないじゃないですか。
マリリン・モンロー(アメリカの女優、モデル)
それでは~。