『レ・ミゼラブル』について

『レ・ミゼラブル』は、ヴィクトル・ユーゴーによって1862年に出版された、フランスの歴史小説。
作家ヴィクトル・ユーゴー 1802年2月26日 – 1885年5月22日
あらすじ
”貧しいジャン・ヴァルジャンはパンを盗んだ罪で監獄に送りこまれて十数年ものあいだ苦しみ、さらに出所後も差別に悩まされる。しかし、ある司教に出会ったことで生まれ変わった彼は、まったくちがう人生を歩きはじめる。” 「BOOK」データベースより
『レ・ミゼラブル』名言集
”法律と風習があるために、社会的処罰が存在し、文明のただなかに人工的な地獄をつくりだし、神意による宿命を人間の不運でもつれさせているかぎり、また貧乏のための男の落伍、飢えのための女の堕落、暗黒のための子供の衰弱という、現世紀の三つの問題が解決されないかぎり、またあちこちで社会的窒息が起こりそうであるかぎり、言葉をかえてもっと広い見地に立って言えば、地上に無知と悲惨がある以上、本書のような性質の本も無益ではあるまい。”
『レ・ミゼラブル』は人間の無知とそれに伴う悲惨さを描いた作品。そして、悲しいことだけれど、この無知と悲惨さがこの世からなくなることはないから、この物語は読了後も読者の心の奥にいつまでも残り続ける。
”聖者になることは、例外である。正しい人になるのが、普通である。迷ったり、怠けたり、罪をおかしてもいいが、正しい人であれ。罪をできるだけ少なくすることが、人間の掟である。全く罪のないというのは、天使の夢だ。地上のすべてのものは、罪を免れない。罪は引力である。”
この本に登場する文章の中で、一番私が好きな文章。「迷ったり、怠けたり、罪をおかしてもいいが、正しい人であれ」『レ・ミゼラブル』の主人公ジャン・バルジャンは、まさにそういう人間であり、彼の生き様が読者に、人生を生ききるとはどういうことなのか教えてくれる。
”「泥棒や人殺しを決して恐れてはいけない。彼らは外部の危険で、それは小さな危険だ。わたしたち自身を恐れよう。偏見、それが泥棒だよ。悪徳、これが人殺しだ。大きな危険は、わたしたちの内部にある。わたしたちの首や財布をねらう者は、大したことはない!わたしたちの魂をねらう者だけを考えよう」”
泥棒や人殺しよりも恐ろしいものは、自分の心の中にある偏見や悪徳。魂がすべてであるのだから、その魂が汚れてしまえば、自らを腐敗へと導いてしまう。他人を恐れず、自分自身に集中して、身魂磨きに専念しよう。
📝関連記事「日月神示に相談しよう:身魂磨きについて」
”ついでに言うが、成功とはかなりいやしいものである。成功とは価値と似ているように見えるために、人はだまされる。大衆にとっては、成功と優秀は、ほとんど同じ顔をしている。才能と瓜二つの成功には、歴史もよくだまされる。ユヴェナリウスとタキトゥスだけが、それに不平を唱えている。現代では、ほとんど公認された哲学が、成功の下僕となって住み込み、成功のお仕着せを着て、控え室で勤めている。成功せよ、これが理論である。出世は能力のある証拠だ。宝くじで儲けよ、そうすればあなたは有能な人間だ。勝った者は、尊敬される。幸運に生まれよ、それがすべてだ。チャンスをつかめ、あとはなんでも手に入れることができる。幸福であれ、そうすれば偉人と思われるだろう。世紀の輝きをなしている五人か六人の大きな例外を除いては、同時代の称賛は多くの場合近視からくるものにすぎない。~彼らは、大空の星座と、アヒルの脚が柔らかい泥の上につける星形とを、混同しているのである。”
「成功」と「価値」の区別を「大空の星座」と「アヒルの脚がつける星形」と表現しているのが面白い。成功とは単に成功であり、それに価値があるかどうかは別だということ。そして、本当に価値のあるものはその時代では称賛されず、大して価値のないものの方が同時代からの称賛を得やすいというのは、悲しいけれど実際にそうであることがほとんどだと思う。
”「ですがね、世界の光景をご覧なさい。万人が万人を相手に戦っている。いちばん強い者が、いちばんすぐれている。あなたの<互いに愛し合うべし>は、馬鹿げたことですよ」ビヤンヴェニュ閣下は、議論せずに答えた。「ところが、それが馬鹿げたことだとしても、牡蠣の中に真珠があるように、魂はその中に秘められていなくてはならないのですよ」”
「できないからやらない」は違う。たとえ出来なくても、取り組む意味がないというわけではない。結果は手に入れられなくても、取り組む、取り組んだというのが大事なことがあるもの。そういうものは、目的地に意味があるのではなく、道中に意味があるから。恋人と食事に行っても、大事なのものが食事でないのと同じ。恋人たちにとって意味あるものは、食事の内容ではなく、二人で過ごした時間だから。
”しかし、ついでに言っておくが、この種の連中と、都市の恐ろしい人殺しとでは、大きな開きがある。密猟者は森に住み、密輸入者は山か海で暮らしている。都会は腐敗した人間をつくるから、残忍な人間もつくる。山や海や森は、野性的な人間をつくる。自然は荒々しい面を発達させるが、人間的な面を破壊することはあまりない。”
西部劇を観ていると、この言葉をより理解しやすいと感じる。西部劇に登場する残忍な人間とは、多くの場合、悪名高いガンマンではなく、都会の権力者たちなのだ。前者は荒々しいが、後者は人間的な面が破壊されたように薄情で、銃こそ持っていないものの(時には銃も持っている!)、残忍である。だから見た目に騙されてはいけないし、見た目では判断できない。
”ご婦人方、あなたがたはアップル・パイが好きだ。だが食べすぎてはいけない。アップル・パイでも、良識と技術が必要だ。大食は大食漢を罰する。神さまからの依頼で、消化不良は胃に向かって説教する。それに、こいつを覚えておきたまえ、われわれの情熱はどれも、恋ですら、胃袋を持っているが、それをみたしすぎてはいけない。何事も、適当なときに終わりという言葉を、書かなくてはいけない。おのれをおさえなくてはいけない。”
大食は聖書でも警告されている・・・。
”あなたが食欲旺盛な人間なら自分の喉にナイフを突きつけたも同じだ” 箴言23章2節
食べ過ぎは、身体の酸化を促し、結果老化につながる。いつでも腹八分を意識して、必要以上に食べ過ぎないようにしたい。まして、空腹でもないのに一日三食は論外。
📝関連記事「日月神示が示す理想的な食事方法」
”ある種の性質の人は、一方を愛するためには、他方を憎まないわけにいかない。”
よく見かける悲しい光景・・・。
こういう人たちは、おそらく本当の愛を知らないのだろう。愛は無限に湧き出て来るものなのに、有限のものだと錯覚し、一部の人間にしか愛を伝えようとしない。憎まれる方は特に理由なく憎まれているわけだから、解決のしようもない。そしてそもそも、このような条件付きの愛は、本当の愛ではないのだ。
”「みなさん、こいつをよく覚えておきなさい。悪い草とか、悪い人間はいないのです。育てる者が悪いだけです」”
シリアルキラーについての報告とか生い立ちを読むと、本当にこの言葉の通りだと思う。どこかで歯車が狂い出し、そして、その歯車を狂わせているのは大抵親とか家庭環境とか、本人の問題というより、外部の影響が大きいから。幼少期の出来事は、人格形成に絶大な影響を与える。もし、自分の性格に疑問があるなら、幼少時代を振り返ることが大きな助けになる。何故なら、人は幼い頃無意識に親やその他の家庭環境から受け取った負のメッセージ(心の傷)に基づいて、その傷を隠すように性格をつくるからだ。
”首相から森林看守にいたるまで、国家の職務についている者には、一種の盲目的な深い信頼を寄せていた。ひとたび法の敷居を踏み越えて悪の道に入った者には、軽蔑と反感と嫌悪を浴びせかけた。断固として、例外を許さなかった。一方でこう言っていた。「官吏が誤るはずがない、司法官は決してまちがいを犯さない」他方ではこう言った。「こいつらは絶対に駄目だ。いいことなんかするはずがない」こうした極端な精神の持主は、人間の法律に、罪人をつくるというか、証明するというか、何とは知れぬ権力を与えて、社会のどん底に三途の川を設ける。”
偏見と思い込みも、極めてしまうとこんな極端な思想になってしまう。だから、これら二つは、なくす努力をしなければならない。
”なんのためでもない。ただどうしても見たり、知ったり、探りたいだけなのだ。ただおしゃべりしたいだけなのだ。そしてしばしばこれらの秘密が知られ、神秘があばかれ、謎が明るみに出されると、破局、決闘、破産、家庭の没落、生活の破壊が起こり、利害関係もなく、単なる本能によって「すべてをあばいた」人たちが、大喜びするのである。悲しいことだ。ある種の人びとはただおしゃべりをしたいために意地悪になる。彼らの会話、サロンでの雑談や、控室での無駄話は、薪がすぐ燃えてしまう暖炉のようなものだ。彼らには燃料がたくさんいる。その燃料とは、近くにいる人なのだ。”
よく見かける光景2・・・。
ただおしゃべりしたいという理由だけで、被害に遭う人たちがいることを思うと悲しくてたまらなくなる。ちなみに、過食と同じく喋りすぎも聖書ではよくないこととされている。
”愚か者の唇は争いをもたらし、口は殴打を招く。愚か者の口は破滅を 唇は罠を自分の魂にもたらす。” 箴言18章6節
”スペインにあったような、また現在チベットにあるような修道院制度は、文明にとって一種の結核である。それは生命をきっぱりと止めてしまう。ごく簡単に言えば人口を減らす。幽閉は去勢である。それはヨーロッパでは災いだった。それにまた、良心にたいしてあんなにしばしば加えられた暴力、強制的な天職、修道院に支えられた封建制、家族の余計者を修道院に送り込む親たち、前に述べたような残虐性、「地下牢」、閉ざされた口、ふさがれた頭脳、永遠の誓いのもとに石牢に入れられた多くの不運な知性、僧服を着たままの魂の生き埋め、などをつけ加えよう。国民の荒廃に個人の苦しみを加えよう。そうすれば、僧衣とベールという、人間の発明した二つの経帷子を見ると、誰でも戦慄を覚えるだろう。”
ズバリ、修道院制度の闇。修道院は刑務所と変わらない。入る時は簡単には入れるが、出ることは難しい。
映画『尼僧物語』を見ると、この闇をより理解することができる。

尼僧物語 (字幕版)
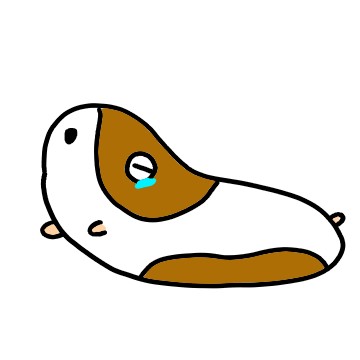
”思惟によって、下の無限を上の無限に接触させること、それが祈りと呼ばれる。人間の精神からは何ものも取上げまい。取上げることは悪いことである。改革し、変形させねばならない。人間のある種の能力、思惟や夢想や祈りなどは、未知なものに向けられる。未知なものとは一つの大洋である。良心とは何か?未知なものへの羅針盤である。思惟、夢想、祈り、それこそ偉大な神秘の輝きである。それを尊重しよう。この魂の荘厳な光は、どこへ進んで行くのか?闇へ向かって、つまり、光明に向かって進むことである。”
祈りとは何かについての一文。祈ることが、良心に耳を傾けることが、暗黒という人生の中で羅針盤の役割を果たしてくれ、それによって光を目指すことができる。
”ニヒリズムには、どんな価値もない。虚無は存在しない。ゼロも存在しない。すべては何ものかである。無は何ものでもない。人間はパンよりもむしろ、肯定で生きている。見て示すこと、それだけでは十分ではない。哲学はエネルギーでなければならない。人間の改良に努力し、その結果を出さねばならない。”
虚無主義の主張も分かるけれど、虚無になっていても人生の問題は何も解決しない。結局、死を選ばず、生きることを望むなら、無ではなく、可能性を見出さなければならない。「どうせ人生は虚無だから」と言っていても何も始まらないのだ。いったん虚無に行き着くのはいい。だけど、生きることを選ぶ以上、いつかはそのどん底から這い上がらなければならないのだ。
”学問は強心剤でなければならない。享楽するとは、なんとつまらぬ目的であり、なんとみじめな野心であろう!畜生は享楽する。考えること、そこにこそ魂の真の勝利がある。人びとの渇望に思想を差出し、すべての人間に妙薬として神の観念を与え、彼らの心の中で良心と学問を和合させ、その神秘的な結合によって、人間を正しいものにする。これが真の哲学の役割である。”
哲学することの意味について。「考えること、そこにこそ魂の真の勝利がある。」魂の勝利をつかむために、考えよう。そのためには疑問を持つことが大切。ぼーっと受け身でいても疑問は生まれない。それは誰かの思想を無意識のうちに植え付けられるだけである。自分の思想は自分で創り上げなければならない。思想は誰かの借り物であってはならない。
”修道院、このまちがっていながら無垢である場所、迷いの場所でありながら善意の場所、無知でありながら献身の場所、苦しみの場所でありながら殉教の場所、それについて語るとき、ほとんどいつも、肯定すると同時に否定せざるをえない。修道院、それは一つの矛盾である。その目的は救済、その手段は犠牲である。修道院は、結果として極度の自己犠牲を持つ極度の利己主義である。~修道院では、享楽するために苦行をする。死の為替手形を振出す。地上の闇の中で、天の光をあてにする。修道院では、天国という相続財産の前金として、地獄を受取る。ベールや修道服をつけることは、永遠によって報いられる自殺である。”
修道院、それは一種の矛盾の場所。信仰心を持つことは良いことだ。問題なのは修道院という場所であり、その場所を構成している、「制度」である。どうして神を信じることに、自分を物理的に鞭打つことが必要なのか。真の意味では善悪は存在しないとすれば、鞭打って当然の行いなんてものも存在しないはずである。
”信仰、それは人間にとって必要なものである。何も信じない人は不幸なるかな!心を奪われているからといって、何もしていないのではない。目に見える労働と、目に見えない労働がある。瞑想することは、働くことであり、考えることは、行動することである。腕をこまぬいているのも、働いていることだし、合掌するのも働いていることである。目を天に向けることも、仕事である。”
人間にとって大切なことであるはずなのに、どんどんないがしろにされている祈りや瞑想。でも、その効果は計り知れない。祈りは病気やケガを癒しそして何よりも祈る人自身の心身を安らかにさせ、瞑想は自分の魂の声を聴くことができる。
”軽率で、せっかちな人は言う。「神秘のかたわらでじっとしているあの人たちが、なんになるか?なんの役に立つか?何をしているのか?」ああ!われわれを取巻き、われわれを待っている暗闇の前で、広大な散乱のためにわれわれがどうなるかわからないが、ただ次のように答えよう。「あの人たちがする仕事以上に崇高なものはないだろう」そして「たぶんそれ以上に有益な仕事もないだろう」とつけ加えよう。決して祈らない人のために、いつも祈っている人が必要である。私によれば、すべての問題は、祈りの中にまじっている思想の量にあるのだ。”
祈りにまつわる数々の奇跡について知れば、信仰についての考えも変わるはず。自分が理解できないからといって、その行為を馬鹿にしてはいけない。
”「~人生を忘れるんだ。人生なんてものは、誰かのいやらしい発明だ、長持ちはしないし、なんの役にも立ちやしない。生きようとするからひどい目に会う。人生は使い道のない飾り物さ。幸福とは、表側だけペンキを塗った古い窓さ。『伝導之書』で言ってる、すべては空なり、とね、こう言った爺さんは、たぶん実在しなかったのだろうが、僕の考えも同じだよ。ゼロは、素っ裸では歩きたくないもんで、虚栄をまとったのさ。」”
それがたとえ真実だったとしても、虚栄の中に、何か価値あるものを見つけ続けることが大事なのだ。人生が虚栄でゼロだったとしても、そこから生まれるもの自体にさえ意味がないわけではない。何故なら、意味は自分で付けるものだから。
”なぜなら、小さな戦いの中でこそ、多くの偉大な行為が行われるからである。窮乏と汚辱の避けられない襲撃に、闇の中で一歩一歩抵抗している、隠れた、粘り強い勇者がいるものだ。誰の目にもとどかず、どんな名声も報いられず、どんな歓呼のラッパの敬意も受けない、気高く、不思議な勝利。人生、不幸、孤独、遺棄、貧乏は、英雄を生む戦場であり、無名の英雄の方が、有名な英雄より偉大なこともある。しっかりした、非凡な性格はこうしてつくられる。貧苦はたいてい継母にあたるが、ときには母ともなる。貧窮は力強い魂と精神を生み、窮乏は自尊心の乳母であり、高潔な人びとには、不幸がよい乳となる。”
不幸には優れた人格を創り上げてくれるという良い一面もある。だから、不幸もありがたく受け入れれば、それによって自らの精神が高められ、結果、幸福につながる。
”考え深い人たちは、幸福な人とか不幸な人という言葉をあまり使わない。明らかにあの世への入り口ともいうべきこの世には、幸福な人など存在しない。人間の真の区別はこうである。輝く人と、暗黒の人。暗黒の人間の数を減らして、輝く人間の数をふやすこと、それが目的である。教育!学問!と人びとが叫ぶ理由はそこにある。読むことを学ぶことは、灯りをつけることである。拾い読みをしたすべての綴りが、光を放つのである。しかも輝きは、必ずしも喜びということではない。輝きの中でも人は苦しむ。過度の輝きは燃える。炎は翼の敵だ。飛ぶことをやめないで燃える、そこに天才の神秘がある。あなたが何かを認識しても、また何かを愛しても、やはり苦しむだろう。光は涙の中に生まれる。輝く人は、暗黒の人間にすぎないような人にたいしても、涙を流すのである。”
輝く人を目指そう。人生が暗黒だからといって、自らも暗黒になる必要はないのだから。そして、輝くことを選んだ人は、人生の多くの局面で、暗黒を選んだ人よりも、苦しむことがあるのだろうが、自らの輝きによって、真の意味では良い人生を体験できるだろう。
”腹黒い政治家のある主張を信じるなら、多少の暴動は、権力という立場からみると、のぞましいものである。この説はこうだ。つまり、暴動が政府を倒さないかぎり、かえって政府を強固にする。それは軍隊を鍛え、ブルジョワを団結させ、警察の筋肉を成長させ、社会という骨格の力を強める。それは体操である。ほとんど健康法でもある。皮膚摩擦のあとで人間が丈夫になるように、権力は暴動のあとで、いっそう丈夫になる。”
多少の暴動は政府にとって体操。そして大衆の起こす暴動の殆どは「多少の暴動」の範疇に収まってしまう・・・。国民全員が!なんてことになれば大どんでん返しは容易なのだが、なかなかそうはならない。
”これ以上望みを持たない人がいる。青空さえあれば、「これで十分だ!」という人間で、驚異に心を奪われ、自然を崇拝して、善悪には無関心たろうとする夢想家で、木陰で夢想できるものなら、他人の飢えや渇きや、冬も裸の貧乏人や、リンパ性彎曲の子供や、不潔なベッドや、屋根裏部屋や、牢獄や、寒さにふるえるぼろ着の少女のことなどに頭を悩ます者の気が知れぬという、人間を忘れた宇宙の観照家であろう。”
過度の楽天主義者は宇宙の観証家。
それは、天体望遠鏡で夜空の星を眺めているのと変わらない。見るべきものは遠い夜空にあるのではなく、自分の周りそこかしこにある。孤独、無知、悲惨。そういう身近な闇から目をそむけて、綺麗な自然や宇宙を眺めることは簡単で、誰にでもできる。難しく、かつ、目指すべき姿勢は、身近な悲惨を知り、向き合いながら、それでも生きる意味を見出すことである。
”ホラティウスも、ゲーテも、おそらくラ・フォンテーヌも、その一族である。無限を求める壮大なエゴイスト、苦痛の冷淡な傍観者で、天気さえよければネロにも目をとめず、太陽に目を奪われて火刑台も眼中になく、光線の効果を知ろうとしてギロチン台の処刑を見物し、絶叫にも、すすり泣きにも、死の喘ぎにも、警鐘にも耳をかさず、五月があれば万事結構だと思い、頭上に緋色や金色の雲さえあれば、満足だと言い、星の光と小鳥の歌がなくならないかぎり、まちがいなく仕合せでいられると思っている。彼らは輝く闇である。彼らは、自分が憐れむべき者だとは気がつかない。”
過度の楽天主義者は輝く闇。
輝く人の中にも本当に輝く人と、実は輝く「闇」の人とがいる。暗黒の世界から光を探し続けることは大切だが、だからといって人生の不幸に目を背けていいわけではない。それは楽天主義者というよりは「自分さえよければ」主義者なのだ。
”だが、やがてまた、最初の聖体拝受の子供みたいな無関心が戻ってきた。彼女は教会に欠かさず行き、ロザリオをつまぐり、祈祷書を読み、家の片隅で「アイ・ラブ・ユー」とささやかれている間、他の片隅で「アヴェ・マリア」をささやき、マリユスとコゼットを、影でも見るみたいに、ぼんやりと見ていた。実は、彼女の方が影だったのだが。ある種の無気力な禁欲状態があって、そこでは魂が麻痺して中性化し、生きて行く仕事とでも呼ぶべきものと無縁になって、地震や災害でもなければ、人間的な感動は、楽しい感動も、悲しい感動も、何も感じなくなってしまう。「そんな信心は」とジルノルマン爺さんは娘に言ったものだ。「鼻風邪と同じだよ。お前は人生から何も嗅ぎ取らない。悪い臭いもだか、いい匂いもね」”
信仰心を持つことは大事だが、それは決して人生について無関心になるというわけではない。自分が抱えている本当の魂の声を殺して「無」になることが信仰というわけではない。信仰とはもっとエネルギーに溢れたものなのだから。
”このような幸福が、真の幸福である。この喜びのほかに、喜びはない。愛こそ唯一の恍惚。そのほかはすべて涙である。愛する、もしくは愛した、それで十分だ。それ以上に求めてはいけない。人生の暗い襞の中に、ほかの真珠は見つからない。愛することは、一つの完成なのである。”
「愛以外は涙」「愛することは、一つの完成」作者ユゴーの伝えたかった重要なメッセージであり、感動的な言葉。
『レ・ミゼラブル』を読んだ感想とまとめ
『レ・ミゼラブル』はとてもとても長い小説ですが、素晴らしい小説です。歴史小説であり、哲学書でもある。わたし自身は小説というよりは哲学書だと思っています。「人生は苦しい」これは多くの人が抱いている思いです。そして作者ユゴーも作品の中で「人生は暗黒である」と言っています。けれど「暗黒の中で光を探し求めること」これが大事なのだと主人公ジャン・バルジャンの一生を通してユゴーは私たちに語りかけています。「絶望することは大事だ。だが虚無になってはいけない」ユゴーのこのメッセージは厳しい人生を生きる上で大いなるエールになってくれます。
『レ・ミゼラブル』は「悲惨な人々」「哀れな人々」を意味しますが、わたしは読み始めた頃、そのあまりの悲惨さに文字通り目を覆い、読むことを途中やめていたせいで、読み終わるまでに一年かかってしまいました。悲惨さと人間の残忍性に自然と涙があふれた箇所も何か所もあります。時には激しい怒りも覚えました。けれど、読み進めていると、最初は悲惨さだけが見えていたのに、悲惨さと同じくらいの希望や情熱や気力などの強いエネルギーが、物語の中に詰められていることに気付いたのです。そして思いました「これは悲しいだけの物語ではない」と。そして実際にそうでした。これは絶望を感じている人への激励の言葉が散りばめられた物語なのです。
だから、本当に長い小説ですが、多くの人に読んで見て欲しいと思います。読めば「光」と「影」は本来一つのものであることがよく分かると思います。人生に「影」を多くみるなら、その見ている数と同じくらい「光」を見つけられるのだということを気付かせてくれるでしょう。
ちなみに・・・
『レ・ミゼラブル』には映画版もありますが、「小説読むのは大変だから・・・」という理由で観るのはオススメできません。というのは、映画版は物語の大まかな筋を理解するのには役立ちますが、私が重要だと思う哲学的要素が抜けてしまっているからです。映画では、今回紹介した名言は登場しません。そして映画版は、原作と少し変えられている部分もあるのでオリジナルをそのまま映像化したものとは言えません。映画もミュージカル形式になっていて楽しめるのは楽しめるのですが、『レ・ミゼラブル』の哲学に触れるには、やはり原作である小説を読むしか方法がないのです。

レ・ミゼラブル (2012) (字幕版)
↓オススメ関連記事↓
