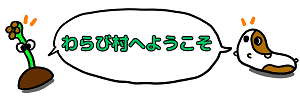みなさん、こんにちは。わらびです。いつも記事をお読みいただきありがとうございます。
人と論争になって、自分が正しいという確信がある時は、主張を曲げることはなかなか出来ませんよね。
けれど、どうでしょうそれで自分の主張を通して、議論に勝って、心がスッキリとするでしょうか。
今回は、このことについて黒住宗忠のエピソードから考えていきます。
無報酬で撫でるだけで多くの患者を治していた宗忠の元へ、ある修験者が次のように怒鳴ってきました。
「あんたは厳しい修行をしたわけでもないくせに、マジナイをして人を惑わしているそうだが、いったいどういうつもりなんだ!」
これに対して宗忠はただ相槌を打つだけで、一言も返しませんでした。
すると修験者は拍子抜けして、宗忠のことを大したことのない奴だと思うと最後に「一言も返すことができない未熟者のくせに、今後説教だのマジナイだのすると承知しないぞ。いいか、もうやめてしまえ!」と捨て台詞を残して去っていきました。
隣の部屋で一部始終を聞いていた妻は「一言も返さないなんて、あんまりではありませんか」と不満を表しました。
すると宗忠は次のように述べたのです。
「わたしが罵られるのは、大したことではない。私が論争にのっていたら、あの方は理を非に曲げて、太神さまのお徳をも汚してしまう。あの方が怒りの矛先を太神さまに向け神様を罵ってしまうことにならないように、私はただ一心に祈っていたのです。それに、もし議論をして、私がそれに勝ったとしても、この世に何も利益はないばかりか、あの方が天から授かった身魂を傷つけるだけだ。それでは、太神さまにたいへん申し訳がない。それよりも、あの方の後ろ姿をみなさい。見事うち勝ったと思う満足の心が見えて、いかにも勇ましいではないか。太神さまはあのような人間のいさぎよい姿を、お喜びなさるのだよ」
そうして宗忠は、遠ざかっていく修験者の後ろ姿に向かって拍手して身魂のご開運を祈ったのでした。
それから一年後、同じ修験者が突然訪ねてきて、宗忠に以前の無礼を涙ながらに謝り、門人にしてほしいと頼んだのでした・・・めでたし、めでたし。
この宗忠のように振る舞うことが出来るようになるには、実際には相当身魂が磨かれていないと難しいと思いますが、大事なポイントは、たとえ議論に勝っても自分のためにはならないということです。
例えば、自分が100%正しいとします。100%正しいのですから、議論に勝つことは出来るかもしれません。そして実際に相手は言い返すことが出来なくなり、自分が議論に勝ちました。
しかし、それは自分が勝ったと思っているだけで、相手はそう思っていません。
多くの人間は自分が間違っていると認めることがなかなか出来ないので、素直に議論に「負けた」とは思わないものです。
どんなに正論を言われても、「自分は間違っていない」と心の中では呪文のように繰り返しています。
たとえ、言い返すことができなくなっても、この「自分は間違っていない」という考えは変わらず、逆にここまで自分に屈辱を与えた相手に対して恨みの念を持ちます。
素直に「わたしが間違っていました。すみませんでした」と言える人はなかなかいません。
そうして、議論が終わるまでなんとか自分のプライドを守り続け、最後に残るのは恨みや復讐心であり、けっして「議論の内容」でも、ましてや、あなたが説いた「正論」でもないのです。
だから、たとえ100%自分が正しくても、議論に勝った場合は、大抵の場合は相手から恨まれたり、復讐心を持たれているので、自分の得にはなっていません。実際は大損です。
敵を作っただけです。
逆に、もし議論に「負けて」いれば、恨まれたり、復讐心を持たれることはないので、敵は増えません。自分が「もう終わったことだ」と済ませることが出来れば、それで終わりです。
だから、どちらが本当は得なのかと言えば、実は議論に「負ける」方なのです。
根に持つ人は本当に根に持つので、そんな人と議論して、もし「勝った」場合は大変ですよ。
ギスギスした関係が長く続き、きついのは結局自分ということにもなりかねません。もちろん、相手もきついでしょうが、こんなこと誰のためにもなっていませんよね。
なので議論になった時は、「議論にのっからない」これが正解です。
勝っても何の得にもなりません。人によっては優越感をおぼえるかもしれませんが、それも一時的です。
その優越感以上のマイナス要素を作ってしまったことにいずれ身を持って知ることになります。
だから議論にはのらず、相手が勝ちたがっているなら勝たせましょう。
自分が100%正しくても、その正論を飲むか、飲まないかは相手が決めることである以上、主張を通すことは出来ません。
正論は相手に無理矢理飲ませることはできないのです。
だから議論は無駄です。話し合いには意味がありますが、議論には意味はありません。
なぜなら議論は、勝ち負けにこだわっていて、自分以外の意見を決して認めようとはしないからです。
けれど、話し合いは意見の相互交換なので、そこから新しい答えが生まれる可能性もあります。
なので、自分のためにも、論争にはのらないようにしましょう。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
↓参考文献↓