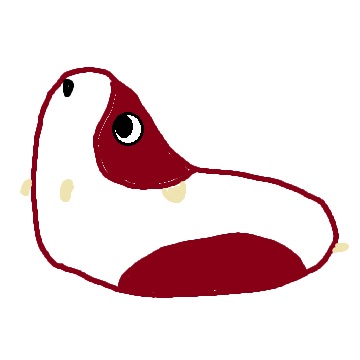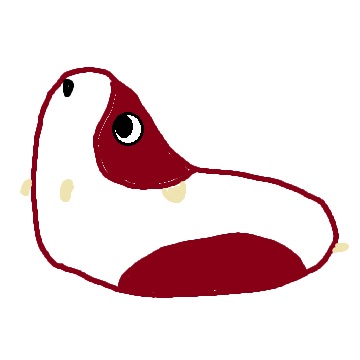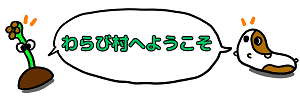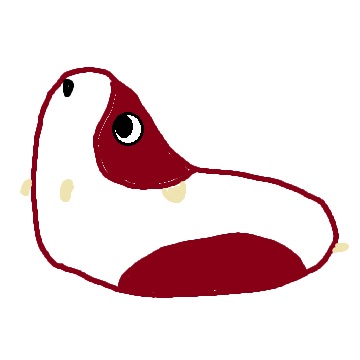
世界三大幸福論の一つと言われているフランス哲学者アランによる『幸福論』。
まだ読んだことがないけれど、どんな内容なのか気になる!という人の為に、自分なりに内容をまとめてみました。
目次
大まかに何が書いてあるのか
ルーアンの新聞に「日曜語録」として連載されたのを皮切りに,総計5000に上るアランのプロポ(哲学断章).「哲学を文学に,文学を哲学に」変えようとするこの独特の文章は,「フランス散文の傑作」と評価されている.幸福に関する93のプロポを収めた本書は,日本でも早くから親しまれてきたもの.折にふれゆっくりと味わいたい.
アマゾン内容紹介より
アマゾンの内容紹介に掲載されているようにこの本は幸福について、もっと言うと「幸福になるにはどうすればいいのか」について書いてあります。
「そのまんまじゃないか!」というツッコミの声が聞こえてきそうですが、その通り「そのまんま」「本のタイトル通り」なんです。
でも「幸福」というと精神的な状態にばかり私たちは目を向けがちですが、「幸福」はまず最初に健康あってのものですよね。
そもそも健康な体でなければ、幸せになりようがありませんから。
アランの『幸福論』が素晴らしいのは、この「健康」の部分にも触れているところなんです。
「幸せになるには~」系の本は世の中にたくさんありますが、健康の部分から触れている本はなかなか少ないと思います。
『幸福論』に書かれていることは大まかに・・・
・病気について
・怒り、心配、不満、悲しみなどの負の感情を持たないようにする方法
・幸せに生きる為の具体的な方法
この3つに分類できます。
病気ではそもそも幸せになれない→だから病気にならない方法→心の中が負の感情に満ちていたらやっぱり幸せになれない→だから負の感情を持たないようにする方法→そして最後に、では具体的にどう生きれば幸せに生きれるのか。
『幸福論』は、こんな風に体系的に幸福について説明されている本なんです。
では、さっそく順に内容を紹介していきます。
病気について
前提:人は病気を作り出すこともでき、病気を悪化させることもでき、他人を病気にすることも、救うこともできる。
【病気を自ら作り出すメカニズム】
①自分の体の調子を異常に心配する。
→心配は恐怖心を生み出す。
→恐怖心は病気を生む。
(対策)少しぐらい調子が悪いぐらいでは、あまり気にかけないこと。ましてや軽々しく医者に診てもらったりしないこと。
②ささいなことで機嫌を悪くし、腹を立てる。
→怒りは精神の病気であり、これにより本物の病気が生まれる。
(対策)怒りや恐怖、悲しみなどの負の感情は、自らの健康にとって害悪であることを理解し、積極的に排除すること。
【他人の病気を悪化させたり、病気にさせるメカニズム】
①悲しんだり、あわれみの言葉をかけること。
→よっぽど相手が精神的に卓越した人でないと、大抵は、これらの行為によって不安や恐怖心が生まれ、病気になってしまう。
→最悪の場合、あわれんだ自分にも恐怖心が生まれ、そのことでやっぱり病気になる。
②「顔色が悪い」などと言う。
→やはり、相手を不安にさせ、そのことで病気を発生させる。
(対策)他人に決して「顔色が悪い」などと言ってはいけない。たとえ、本当にそう見えたとしても。初期の病気はそれに気づいてしまうことで、本当に病気になってしまう。逆に言えば、病気の兆候が本当にあったとしても、それに気づかなければ病気にならないことが多い。
〇この項のまとめ〇
アランは「病気とは自分で作り出すものだ」と言い切っています。それで、本の中で驚いてしまうくらい病院を否定しています。何故なら病院は些細な病気の兆候を見つける場であるからです。些細な兆候を見つけてしまうと、大抵の人は心配になっておびえるから、本当の病気になってしまう。だったら、そんな病院なんて行かずに、兆候に気付かなければ、病気にはならない、と言っているのです。「病は気から」という言葉にも似ている考えですね。
怒りや心配などの負の感情を持たないようにする方法
【人が負の感情を持つメカニズム】
①些細なことが原因
→歩き疲れて足が痛かったから。肌着の着心地が悪かったから。驚いたから・・・などなど
②血球の数
→血球の数が多い時には機嫌が良く、血球が少ない時には機嫌が悪くなる傾向にあることが、ある患者の研究によって明らかになっている。
③暇だから
④過去を振り返るから
①の「些細なことが原因」について
人はほんのちょっとしたことが原因で、簡単に機嫌が悪くなったりする。
”ほんのちょっとしたこと”というのがポイントで、この原因を見つけ取り除くことで、この問題を解決することができる。
”ほんのちょっとしたこと”とは、(肌着の着心地が悪いのかもしれないし、新品の靴がまだ自分の足に合っていないのかもしれないし、歩き疲れたから)なのかもしれない。
それはちょうど、お腹が空いたり、オムツが気持ち悪くなって泣きわめく赤ちゃんと同じ。些細なことで機嫌が悪くなるという意味では、大人も赤ちゃんもそうは変わらないと心に留めておくこと。
②の「血球の数」について
何の原因もなく不機嫌になっているのは、血球のしわざなのかもしれないから、それ以上には考えないこと。
③の「暇だから」について
暇だと人は自分のことを考えすぎるようになる。けれど考えたところで上手な説明を見つけることはできないから、イライラする。音楽や読書、仕事や友人を活用して暇な時間を作らないようにすれば良い。
④の「過去を振り返るから」について
過去を振り返り見つめることは悲しみを生む。なぜなら、無益な反省をさせ無益な探求をさせるから。過去のことは、どうしようもないのだから今に集中する。
【それでも負の感情を抱いてしまったときには・・・】
簡単な体操をすることで解決できる。人間の気分というものは筋肉の動きと直接的に関係している。笑顔でいながら怒ることはできないように、不機嫌なときは意識して笑顔を作るようにすれば良い。
逆に機嫌の悪い時に「機嫌を良くしよう。」と精神論でどうにかしようとすることは無意味。想像力によって生み出された悲しみや恐怖心の力は強力だから、これを意思の力でどうにかしようとすることは不可能。
しかし、こんな場合でも人間は自分の筋肉については働きかけることができる。微笑んだり、陽気なダンスを踊って見たりすることで、負の感情を取り除くことができる。
ステージに立つ前はガタガタ震えていたのに、いざステージに立って、喋り出したり、演奏し始めたりすると、震えがピタッとおさまるのと同じ原理。
もう1つ例として挙げられるのが宗教。
宗教によって救われる人が多いのは”祈る”という行為が、この体操になっているから。体操によって筋肉をほぐしているから、心がそれに影響され楽になるのであり、奇跡が起こっているとかそういうわけではない。
〇この項のまとめ〇
この項で重要なのは「機嫌が悪くなっているときに精神論でどうにかしようとしても無駄である」ということです。それだけ、怒りや悲しみや心配などの想像力から生み出された感情は強力であるとアランは述べています。精神論でどうにかするのではなく、「原因を見つけ出すか。機嫌の良いマネをするか。」難しいことは考えても無駄なんだから、このどちらかをさっさとやってみろ!とのことです。
幸せに生きる為の具体的な方法
逆に不幸であるとは・・・
病気であること。不機嫌であること。
→これらは自らの思いで作り出していることがほとんど。
→つまり、不幸は自ら選択している。
Q.それでも現実には不幸な出来事はあるじゃないか!
A.確かにある。しかも多い(アラン談)。けれど言い出せばキリがない。それに悲しみは悲しみを生み出すもの。だから、どこかで断ち切る必要がある。
例えば雨について文句を言ってもどうしようもない。文句を言っても雨が降るのを止めることはできない。そうではなくて逆に感謝する。すると喜びによって体が温まり、雨に濡れても風邪をひかなくなる。

それに、本当の不幸をいうのは、想像している不幸とは全く違うものである。
本物の不幸というものは、一瞬。
悲しんだりする余裕もなく一瞬に過ぎ去る。
つまり、自分が想像するより不幸は苦痛ではない。
まさに”死に恐れるものは生者のみ。不幸の重荷を考えるのは幸福な人のみ”なのである。
【要するに「常に楽観主義であれ」ということなのだが、「そんなことムリ!」という人へ】
「ムリ」と思うならムリ。なぜなら、上機嫌というものは存在せず、自らの意思や行動で作り出すものだから。
上機嫌であることは、混乱した世の中で生きていくことを容易にする最良の方法でもある。上機嫌はまず本人を幸せにする。そして上機嫌でいると自分の周りに起こる出来事が変わる。誰でも機嫌が悪い人よりも、良い人を好むから。
どんな時でも感謝の言葉を口にすること。どんな失礼な人にも親切にすること。それが上機嫌でいることの秘訣である。
幸福に生きるには・・・「幸福に生きる」という強い意志が必要
なぜなら
①人は自分の気分のままに生きていると必ず悪い方向へ進むから
人間は本質的には悲観主義であるから、信じたり、希望したり、笑顔でいたり、目標に向かって努力するなどして、積極的に楽観主義を取り入れなければ、怒りや絶望に苦しむことになる。
②社会は自ら求めるところのない人には何も与えないから
ようするに”棚からぼた餅”はナイってこと。
”求める”というのは絶えず継続するということで、これには忍耐や勇気が必要。
何かを求めたのにそれを手に入れられないのは、その人がそれを本当には欲していなかったから。それを手に入れる為に当然すべきだったことをしてこなかったから。
”欲する”というのは希望することとは違う。
希望は単に願っているだけ。”棚からぼた餅落ちてこないかな~”と口を開けて待っている状態のこと。
これに対して”欲している”とは、それに向かって行動すること。ぼた餅を求めて出かけている状態のこと。
つまり、幸福になるには幸福になるための行動が必要ということ。
”棚からぼた餅はナイ”について
幸福は探して見つかるものではないということ。
幸福というのは、状態のことである。つまり、幸福は自分がそれを有しているときでなければ、幸福ではない。
一見、棚ぼたっぽい幸福があったとしても、それは真の幸福ではない。
なぜなら出来合いの幸福とは、すぐにそれを手に入れた人から離れていくから。すぐ離れていく幸福はもともと存在していなかったのと同じ。
登山家が見る山頂からの景色と、ロープウェイで山頂まで登った人が見る景色の見え方が違う理由がここにある。登山家は自分で獲得した景色であるのに対して、ロープウェイを使ってみる景色は与えられた景色であるから。
幸福というものは砂糖のように味わうものでも、味わえるものでもない。
音楽もそれを聴く人よりも、歌ったり、演奏したりしている人が一番楽しんでいる。絵でも、舞台でも同じ。観客よりもそれを実際にやっている人が最もそのことにより幸福を得ている。
これが”幸せ=行動”であることの理由。
しかし、人は行動したがらない・・・
最終的に幸福になる人は、報酬を得ようと努力する。例えば山頂からの景色を見てみたいなど。そして、その過程のなかで、足腰が強くなったり、体力がついたりなどの別の報酬を獲得する。
実はこの別の報酬が真の報酬である。
そしてこの別の真の報酬が、さらなる報酬につながる。
けれどずっと不幸な人は、見かけの報酬とそれを得るための苦痛とだけを比べて行動しない。
だから、真の報酬に気付きようがないから、余計に行動しない。行動しないから退屈になり、退屈になるから不機嫌になる。
つまり、このいつまでも幸せになれない人は、先に幸福を見つけなければ行動しようとしない。けれども真の幸福というものはまず苦痛を要求する。これがずっと不幸である人が存在する理由である。
【幸福に生きるためにすべき具体的なこと】
・「幸福になる」と誓うこと
・悲しみや怒りなどの負の感情をすべて否定し取り去ること
↑ここまでは前述済み
・”今”に集中すること
”今”に集中すること
過去を振り返ると不幸になる理由は既に述べたが、では何故将来について考えることもダメであるのか。
それは、将来のことは予見できないから。(アランは占いを否定している。そして占ってもらうことは非常に危険であると注意している。)
そして将来を作るのは現在の行動だから。
”行動=幸せ”だから、”今”行動することが将来の幸せを作り出すことになる。
だから最初は希望なしでやらなければいけない。「今はまだその時期ではない」と先延ばしにしてはいけない。将来はそもそも予見できないのだから。今が良いタイミングなのか悪いタイミングなのかは分かりようがない。こんなことを言っている人は一生良いタイミングはやってこない。
希望よりも信念を強く持つこと。
用心深い計算は常に苦痛に満ちており、心配は希望も打ち消してしまう。だから、タイミングを見計らったり、変に計算したりせずに思い切ってやることが大切。
行動してからあとのことを考える。良いタイミングも悪いタイミングも本質的には存在せず、どのタイミングも人によっては良いタイミングになる。
【不必要な恐怖心を抱かない為には・・・】
本当に大事なことだけを見極める。例えば荒れた海が目の前にあるとき、海が荒れているということは重要ではない。真の問題は、もし海に落ちたとして”頭が水面に出せるか、出せないか”ということである。何故なら荒れていない静かな海でも、おぼれるときはおぼれるのだから。
【”今”に集中するために・・・】
余計なことに心を惑わされない。
幸福である人は、常に自分の目標に集中している。これに対して、いつまでも不幸な人は、ありとあらゆるムダなものに首をつっこみ、何もせずに人生を終える。
「今の自分にこれは本当に必要なものだろうか?」と問いかけ、そうでないものは取り除いていくことが大事。
〇この項のまとめ〇
過去も、将来も見ずに、今に集中して行動しろ、ということですね。よく幸福について書かれた本は最後「今に集中しろ」という内容で締めくくられているものが多いのですが、この本にも同じことが書かれていて驚きました。やはりこれは真実なのでしょう。
まとめ
以上、アラン『幸福論』のまとめでした。
「幸福とは探すものでも、味わうものでもない。幸福とは自らの行動によって獲得するものであり、状態のことである。」というのが、印象的な内容でした。
本の中には、今回紹介したこと以外のことについても語られているので、面白そうだなと興味を持った人は是非本も読んでみてください。
それでは~。
↑この本は93のプロポ(=哲学断章:短編のエッセイのようなもの)で構成されており、1プロポにつき大体2~3ページです。なので、最初から順に読んでいくのも勿論良いのですが、気になった箇所から読んでいくという読み方もできます。文が独特で「読みにくい」と感じる人もいるかもしれません。でもゆっくり、じっくり文を味わっているうちに、アランの辛口なコメントにププッと笑ってしまう余裕ができ、そうなった頃にはどんどん引き込まれて読み終わっていた、となる不思議な魅力がこの本にはあります。